坂の上の雲 老舗MAP 「住む」
松末商店
「山より大きい獅子は出ん」地域と共に
駅で開けた町に、文明開化の産声を上げて
 伊予鉄道横河原線を走る蒸気機関車 明治32年に伊予鉄道横河原線が全線開通すると、それまでわずか10数戸の小集落でしかなかった横河原は、ようやく町の規模へと発展しはじめた。
伊予鉄道横河原線を走る蒸気機関車 明治32年に伊予鉄道横河原線が全線開通すると、それまでわずか10数戸の小集落でしかなかった横河原は、ようやく町の規模へと発展しはじめた。
当初、松末商店はその横河原駅前に位置して、松末磨多一さんが大正2年に製材業を創立。工場や木材置き場に専用の引込線が敷かれ、三津浜や高浜から広島方面にまで直結するルートを確保。
横河原の主力産業として、市駅に次ぐ貨物流通の一大拠点の礎を築いた。
界隈には工場の動力源だった焼玉エンジンの大きくリズミカルな音が響いた。駅に乗合馬車が出入りする時代、それは横河原の人々に文明の息吹を思わせる画期的な光景だった。
創業は、実に356年前
 旭館で催された芝居 磨多一さんは業界では名の知れた世話役で、度量の大きいひとだった。新しい物好きで駅のすぐ側に旭館を開設。芝居や相撲の興行なども引き受けた。けれど57歳で他界。長男は戦時中の航空事故で亡くなったため、次男の一正さんが27歳の若さで二代目を継ぐことになった。一正さんは9人兄弟。30人に及ぶ従業員とその家族に加え、残された母親はもちろんのこと小学生の弟の世話も背負い、自らも5人の子どもの父親でもあった。その後80余歳で退職するまで、働き詰めで一家の長の大任を果たし続けた。
旭館で催された芝居 磨多一さんは業界では名の知れた世話役で、度量の大きいひとだった。新しい物好きで駅のすぐ側に旭館を開設。芝居や相撲の興行なども引き受けた。けれど57歳で他界。長男は戦時中の航空事故で亡くなったため、次男の一正さんが27歳の若さで二代目を継ぐことになった。一正さんは9人兄弟。30人に及ぶ従業員とその家族に加え、残された母親はもちろんのこと小学生の弟の世話も背負い、自らも5人の子どもの父親でもあった。その後80余歳で退職するまで、働き詰めで一家の長の大任を果たし続けた。
少年時代の遊び場がやがて職場に
 現在の松末商店 松末商店では、戦後はみかんや酒などの箱材が主力商品だった。創業以来、原木は地元山之内の松を使用。昭和40年頃までの20年ほどは100%国産材を扱った。昭和45年には、会社を現在の重信川沿いの樋口に移転した。
現在の松末商店 松末商店では、戦後はみかんや酒などの箱材が主力商品だった。創業以来、原木は地元山之内の松を使用。昭和40年頃までの20年ほどは100%国産材を扱った。昭和45年には、会社を現在の重信川沿いの樋口に移転した。
木材置場は町内の子どもたちの格好の遊び場だった。一正さんの長男で現在代表の秀雄さんには、少年時代いつも見とれていた光景があった。それは原木を薄板に加工した後、水分を乾燥し易くするために螺旋状に積み上げた4メートルほどの“木製タワー”だった。この薄板の山を乾燥後に回収する際に、一気にバサッと崩す。その音と光景がいまでも強く印象に残っているという。
昭和45年に大学卒業後、秀雄さんは自ら外材の丸太や製品を扱う神戸の商社に勤めた。その頃家業が外材に転換したこと、いずれ後継者になる立場を踏まえてのことだった。
しかし大学の邦楽部で2年ほど尺八を習い、準師範の試験を受けた際に首席を取った。その時は尺八のプロへの道も考えた。しかし才能への不安や長男としての立場、親に対する申し訳なさなど心は揺れたが、踏み込むことができなかった。
景気の動向と社会のニーズに対応
 松末商店の製材 昭和30年代半ばからの高度成長期には作れば売れる時代が続いた。だが、昭和48年のオイルショックでその状況が一変する。そして製材業も低迷期が続いた。思いもよらない転機が訪れたのは同62年。国産材を扱っていた近くの同業他社の撤退によって、そこの主だった機械類を引き取ることになった。それを機に外材から国産材に戻すとともに、梱包やパレットなどの箱材から建築材へと切り替えた。すると、内需拡大政策を受けて、10年にわたり低迷していた建築業界が盛り返し、それによって業績が好転。その後、平成6年までは順調に利益を上げた。
松末商店の製材 昭和30年代半ばからの高度成長期には作れば売れる時代が続いた。だが、昭和48年のオイルショックでその状況が一変する。そして製材業も低迷期が続いた。思いもよらない転機が訪れたのは同62年。国産材を扱っていた近くの同業他社の撤退によって、そこの主だった機械類を引き取ることになった。それを機に外材から国産材に戻すとともに、梱包やパレットなどの箱材から建築材へと切り替えた。すると、内需拡大政策を受けて、10年にわたり低迷していた建築業界が盛り返し、それによって業績が好転。その後、平成6年までは順調に利益を上げた。
ところが平成7年の阪神淡路大震災で、業界の予測を覆す事態が起きた。「復興で忙しくなる」とささやかれたが、「木造は地震に弱い」とされ、ツーバイフォーなどの屋根の軽い建築材に流れが変わっていった。また建築工期の短縮化が進み、乾燥した木材のニーズが高まり、平成8年には、乾燥機第1号を導入した。
さらに平成12年頃から集成材をスタート。角材の芯まで乾かすことが技術的に困難だったことから、板状にして乾かしたものを接着することで歪みの少ない高品質の製品に仕上げ、これが新たな販路の確保に繋がった。
環境問題に対応 木くず焚きボイラーの導入
 木くず焚きボイラー 平成8年に京都議定書が制定されると、さらに環境問題への取り組みが問われはじめた。松末商店でも事業内容を見直し、それまで活用していなかった木の皮を生物資源の一つとして粉砕し商品化。四国電力の西条火力発電所に売り、石炭に混ぜて電力を生みだすエネルギーとして利用されている。平成14年頃には重油の燃料コスト対策と併せて、わずかながらも二酸化炭素削減をめざして、木くず焚きボイラーを導入した。
木くず焚きボイラー 平成8年に京都議定書が制定されると、さらに環境問題への取り組みが問われはじめた。松末商店でも事業内容を見直し、それまで活用していなかった木の皮を生物資源の一つとして粉砕し商品化。四国電力の西条火力発電所に売り、石炭に混ぜて電力を生みだすエネルギーとして利用されている。平成14年頃には重油の燃料コスト対策と併せて、わずかながらも二酸化炭素削減をめざして、木くず焚きボイラーを導入した。
地域活動に積極的に参加 “山より大きい獅子は出ん”
 松末商店 代表の秀雄さん 秀雄さんは28歳で実家に戻って以降、現・東温市消防団に入団し2年前からは消防団長を務めている。平成6年から3年連続、横河原観月祭で知られた横河原商工連盟会長を務め、平成18年から現在まで再度会長に就いている。
松末商店 代表の秀雄さん 秀雄さんは28歳で実家に戻って以降、現・東温市消防団に入団し2年前からは消防団長を務めている。平成6年から3年連続、横河原観月祭で知られた横河原商工連盟会長を務め、平成18年から現在まで再度会長に就いている。
かつて秀雄さんは、気が弱くて臆病な自分に対して、寡黙な父から“山より大きい獅子は出ん”という力強い言葉を贈られた。社長業とともに重責ある地域活動に努める秀雄さんは、いつの間にかその言葉を木材のように静かに吸いとってエネルギーにしてしまったのかもしれない。

 HOME
HOME



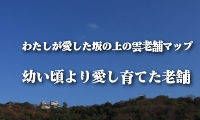
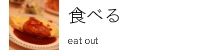









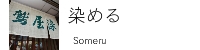




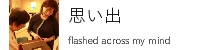
 Homeへ
Homeへ